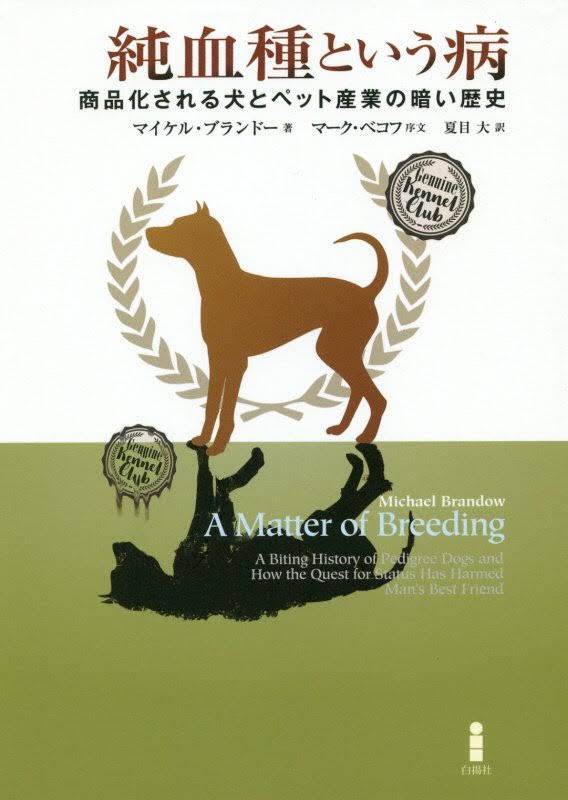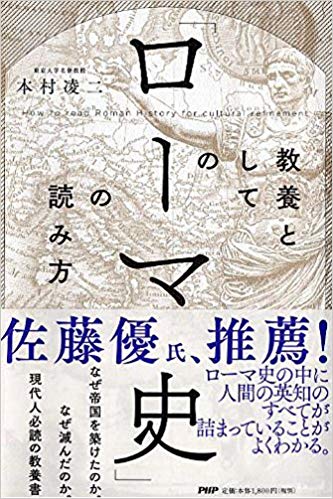どーも、幼児にサンタクロースはいないことを教えてあげるのが好きな悪趣味の早川です。今日はクリスマス。日本ではなぜかクリスマス・イヴのほうが盛り上がりますが、本当のクリスマスは12/25。なぜ日本のクリスマスはイヴがほんまもんみたいな顔をしているのか。いやしかし、そもそもクリスマスとは何だろう。イエス・キリストの誕生日は本当に12/25なのか、サンタクロースは実在するのか。なぜサンタクロースはトナカイがひくソリに乗って煙突から侵入し、こっそり靴下にプレゼントを置いていくのか。普通に考えれば、サンタクロースが子供をおこして直接プレゼントを手渡すほうが子供は喜ぶ。これぞ本物のサプライズでしょ。しかし、サンタクロースはそうしない。なぜだろう。
こういったクリスマスに関する色々な疑問って、人それぞれあると思う。でもその疑問に明確に答えてくれるものって、あまり聞かない。サンタクロースはコカ・コーラのマーケティングだとか、クリスマスとサンタクロースに関するいろいろな伝説はあるけど、それら一つ一つを丁寧に史料にあたって真偽していったのが本書『クリスマスの歴史 祝祭誕生の謎を解く』です。

結論を先に書くと、クリスマスとはあなたが思い描くクリスマス、そして他者が思い描くクリスマス、そういった色々なクリスマス像が重なってできたものだ。したがって「クリスマスとはこうだ」と断定するように定義づけるのは難しい。著者はこう書く。
クリスマスは長い年月のあいだにみずからの姿を変容させてきた。クリスマスは貴族や大地主が使用人や小作人に富を顕示していた時代から、大人がなけなしの金をはたいて浮かれ騒いだ時代へ、そして何よりもまず子供が中心のお祭りになった時代へと移り変わってきた。エリート階級から大衆へ、大人から子供へ、共同体から家庭へと主役が代わるなかで、クリスマスは姿を変え、生き残り栄えてきた。なぜならクリスマスとは今あるものではなく、今まであったものでもなく、私たちがこうあってほしいと思うものだからだ。
だから、この記事の題名にもある「なぜ日本のクリスマスはイヴがほんまもんみたいな顔をしているのか?」に対する回答は、日本人がそう願うからそれでいい、これが答えです。仮にそれが商業主義にどっぷり浸かっていようと、あるいは下のツイートのように渋谷のラブホがイヴに行列ができる「イヴはカップルで」みたいなイメージであろうと、それはどちらも正しい。クリスマスはカメレオンみたいな存在なのです。
そんなクリスマスの起源は『クリスマスの歴史 祝祭誕生の謎を解く』によると4世紀前半とされるから、約1700年も昔のことになる。最初はキリスト教の祝日と定められたクリスマスだが、その30年後には人々は過度に飲食したり、踊りまくったりして、世俗的な楽しみを満喫していた。なんだ、今とかわらないじゃない。そこに贈り物の習慣が加わり、さらにサンタクロースも加わり、クリスマスカードも加わり、現代の商業主義も加わりと、繰り返しになりますがクリスマスは人が望むような姿に常に変わってきたのです。
これだけ複雑なクリスマスの実態を表現するのは難しい。だからクリスマスに関する単純な理解は困難です。私たちは物事の理解をするには、その原因をつい単純なものに帰してしまう傾向があります。でもそれじゃダメで、複雑なものは複雑のものとしてしか捉えられない。理解する過程で一時的に単純化するのは問題ないけど、やっぱり最後には複雑なものとして接しないといけない。そうでないとなかなか深い理解に達せないから。クリスマス一つとっても、世の中はみんなが思っている以上にはるかに複雑だと分かりますね。
- おすすめ度★★★
- お買い得度★★
- 読み応え度★★★
- 一気読み度★★